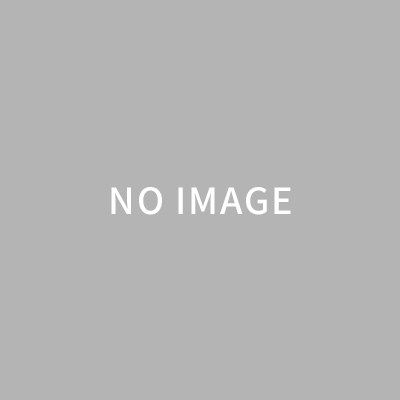「歯周病になりやすい人の特徴とは?」
「自分が歯周病になりやすい体質・習慣をしているか知りたい」
「歯周病を予防するために具体的に何をすればよいのか知りたい」
上記の疑問をお持ちの方は、仕事が忙しく歯科検診を後回しにしてしまい、自身の口内について気になり始めているのではないでしょうか。
歯周病になりやすい人の特徴には、「歯磨きで磨き残しが多い」「仕事のストレスや睡眠不足が続いている」「つい甘いものや間食に手が伸びてしまう」などが挙げられます。
本記事では、「歯周病になりやすい人の特徴や、 歯周病を予防する方法」を紹介します。
歯周病を放置した場合のリスクまで紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。
目次

歯周病は、自覚症状がほとんどないまま進行し、最終的に歯を失う原因となる細菌感染症です。
初期は歯ぐきの腫れや出血といった軽い症状しかなく、痛みはほとんどありません。
気づかないうちに歯を支える骨が溶かされ、病状が悪化するケースも多いです。
また、歯がグラグラする症状が出たときには、すでに手遅れに近い状態も少なくありません。
静かに進行することから「サイレント・ディジーズ(静かなる病気)」とも呼ばれる、注意が必要な病気です。

歯周病になりやすい人の特徴は、以下の10つです。
それぞれ解説します。
毎日の歯磨きでプラークを確実に除去できていないことが、歯周病の最大のリスクであり原因です。
歯周病はプラークという細菌の塊が原因ですが、自己流の磨き方では歯と歯の間や奥歯に磨き残しが生じやすいです。
毎日しっかり磨いているつもりでも、歯ブラシだけでは汚れの6割程度しか落とせていない場合もあります。
ただ磨くだけでなく、プラークを確実に除去する意識と技術が重要になります。
喫煙は、歯周病の進行を早め、治療の効果も下げる最大の危険因子のひとつです。
タバコに含まれるニコチンは血管を収縮させ、歯ぐきの血流を悪化させます。
血流が悪くなると、歯ぐきへの酸素や栄養の供給が滞り、細菌への抵抗力も弱まりやすいです。
治療をしても治りにくくなるため、喫煙者の方はとくに注意が必要です。
仕事や私生活でのストレスや睡眠不足は、体の免疫力を低下させ、歯周病菌への抵抗力を弱めます。
ストレスを感じると体は緊張状態になり、唾液の分泌量が減ることがあります。
唾液には口内の細菌を洗い流す自浄作用があるため、唾液が減ると細菌が繁殖しやすくなりやすいです。
心身のコンディションを整えることは、お口の健康を守るうえでも大切です。
甘いものや間食の習慣は、歯周病のリスクを高めます。
糖分、鉄分、タンパク質は歯周病菌の栄養源となり、菌の活動を活発にさせやすいです。
また栄養源により歯周病菌が増殖し、プラークを形成しやすくなります。
時間を決めずにだらだらと間食を続けると、口内が常に酸性の状態になったり、細菌に栄養を与え続けてしまい細菌が活動しやすい環境が続いてしまいます。
食生活の見直しも、歯周病予防の重要なポイントです。
自分では除去できない歯石の蓄積を放置し、専門家による早期発見の機会を逃している場合も大きなリスクです。
プラークが硬化してできた歯石は、歯磨きでは取り除けません。
歯石の表面はザラザラしているため、さらにプラークが付着しやすくなる悪循環を生み出します。
定期的に歯科医院で専門的なクリーニングを受けることが、お口の健康維持には不可欠です。
歯並びが悪いと、歯ブラシが届きにくい場所にプラークが溜まりやすく、意図せず歯周病のリスクを高める場合があります。
歯が重なっている部分やデコボコしている部分は、どんなに丁寧に磨いても磨き残しが生じやすい場所です。
そうした箇所にプラークが蓄積し続けることで、部分的に歯周病が進行するケースは少なくありません。
そのため、ご自身の歯並びに合わせたケアの方法を知るのが大切です。
全身の健康状態は口内の環境に直接影響し、とくに糖尿病は歯周病と相互に悪影響をおよぼし合う密接な関係にあります。
糖尿病の方は免疫機能が低下しやすく、細菌感染への抵抗力が弱まるため、歯周病が重症化しやすい傾向があります。
逆に、歯周病菌が出す毒素が血糖コントロールを妨げやすいです。
とくに、持病のある方は医科と連携した管理が重要です。
口呼吸は口内を乾燥させ、歯ぎしりは歯や歯ぐきに過度な負担をかけることで、歯周病を悪化させる一因となります。
口で呼吸をすると唾液が乾き、細菌を洗い流す作用が弱まりやすいです。
また、歯ぎしりによる強い力は、歯を支える組織にダメージを与え、歯周病の進行を早める場合もあります。
これらの癖は無意識におこなっている場合が多いため、意識的な改善が必要です。
女性ホルモンの変動は、特定の歯周病菌の増殖を促し、歯ぐきを炎症させやすくします。
とくに妊娠中や更年期には、女性ホルモンの一種であるエストロゲンの分泌量が増減しやすいです。
一部の歯周病菌はこのエストロゲンを栄養源として増殖するため、この時期はとくに歯ぐきの腫れや出血がしやすくなります。
そのため、ライフステージに合わせた特別な口腔ケアが求められます。
遺伝的な体質や、生活習慣・口内細菌の共有により、家族に歯周病の人がいるとご自身の歯周病リスクも高まる傾向にあります。
歯周病になりやすい体質が遺伝することや、同じ食生活で似た口内環境になることが理由として挙げられます。
ご家族のお口の健康状態にも気を配ることが大切です。

歯周病は、「プラーク」という細菌の塊が引き起こす感染症であり、このプラークコントロールが予防の鍵です。
プラークは単なる食べかすではなく、1mgの中に1億個以上もの細菌が存在する細菌の集合体です。
このプラーク内の歯周病菌が出す毒素によって歯ぐきに炎症が起き、やがて歯を支える骨が溶かされてしまいます。
歯周病を防ぐには、このプラークを日々のケアでいかに取り除くかが重要です。

歯周病そのものではなく、原因となる「歯周病菌」が唾液を介して人から人へうつる可能性があります。
歯周病は風邪のように空気感染するわけではありませんが、細菌感染症の一種です。
親子間での食器の共有や、夫婦・パートナー間でのキスなど、唾液が接触する機会があれば菌が移動するリスクはあります。
ただし、菌がうつっても必ず発症するわけではなく、その後のケアや免疫力が大きく関わります。

歯周病を放置した場合のリスクは、以下の5つです。
ひとつずつ解説します。
歯周病が進行すると、膿やガスが発生し、周囲に気づかれるほどの強い口臭の原因になります。
歯周ポケット(歯と歯ぐきの間の溝)が深くなると、そこに溜まったプラークや歯石から、歯周病菌が強烈な臭いを放つガスを産生します。
これは生理的な口臭とは異なり、歯磨きをしてもなかなか消えないのが特徴です。
口臭は、体が発する危険信号のひとつとなります。
歯周病の最も恐ろしい結末は、自覚症状がないまま歯を支える骨が破壊され、健康な歯でも失ってしまうことです。
歯周病菌が出す毒素への体の防御反応として、歯を支えている歯槽骨が溶かされていきます。
骨が溶けると歯は支えを失ってグラグラし始め、最終的には自然に抜け落ちてしまうのです。
虫歯でもない健康な歯を失う最大の原因が、この歯周病です。
歯周病菌が血管を通って全身に広がり、糖尿病や心筋梗塞など、命に関わる病気のリスクを高める場合があります。
たとえば、炎症を起こした歯ぐきの血管から歯周病菌やその毒素が体内に入り込み、血流に乗って全身を巡ります。
それらが体の各所で悪影響をおよぼし、さまざまな病気の発症や悪化に関与するのです。
お口の健康は、全身の健康と密接につながっています。
歯周病は、糖尿病や心血管疾患、誤嚥性肺炎や早産など、さまざまな全身疾患との関連があるとされています。
たとえば、歯周病は血糖コントロールを悪化させ、逆に糖尿病は歯周病を悪化させるといった双方向の関係があります。
また、歯周病菌が動脈硬化を促進し、心筋梗塞や脳梗塞のリスクを高めることも指摘されています。
歯周病の管理は、多くの病気の予防につながるのです。
歯周病は、進行してからでは治療が複雑になり、期間も費用も大幅に増大します。
初期の歯肉炎であれば、丁寧な歯磨きや歯科医院でのクリーニングで改善が見込めます。
しかし、骨が溶ける段階まで進行すると外科的な処置が必要になるなど、治療が大掛かりになりやすいです。
早期発見・早期治療が、結果的に心身と経済的な負担を軽くします。

歯周病を予防する方法は、以下の5つです。
それぞれ解説します。
歯周病の予防の基本は、自己流ではなく、プラークを確実に除去できる正しいブラッシングを毎日実践することです。
ただ時間をかけて磨くだけでは、汚れが残りやすい場所のプラークは除去できません。
歯と歯ぐきの境目に歯ブラシを45度の角度で当て、優しく小刻みに動かすなど、効果的な磨き方を身につけるのが重要です。
また、歯科医院でご自身に合った磨き方の指導を受けるのが最も確実です。
歯ブラシだけでは約6割しかプラークを除去できず、歯と歯の間の清掃には補助的な清掃用具の使用が必須です。
歯と歯が接している面や重なっている部分の汚れは、歯ブラシの毛先に届きません。
そのため、デンタルフロスや歯間ブラシを毎日使うことで、これらの場所に残ったプラークを効果的に除去できます。
歯ブラシと合わせることで、プラークの除去率もより高まります。
バランスの取れた食事で体の免疫力を高め、よく噛んで唾液の分泌を促すことも予防につながります。
歯ぐきも体の一部であるため、ビタミンなどの栄養素は健康な状態を保つために欠かせません。
また、よく噛むことは唾液の分泌を促進し、口のなかの細菌や食べかすを洗い流す自浄作用を高めます。
規則正しい食生活が、お口の健康を支える土台となります。
禁煙をはじめとする生活習慣の改善が、歯周病のリスクを大幅に低減させます。
喫煙は、歯周病の進行を早める危険因子です。
そのため禁煙すれば歯ぐきの血流が改善し、細菌に対する抵抗力が高まります。
また、十分な睡眠やストレスの管理も体の免疫力を維持するために重要です。
生活全体の見直しが、結果的に歯周病予防につながります。
セルフケアには限界があり、専門家による歯石の除去やチェックを受けることが、予防を完璧にするために不可欠です。
どれだけ丁寧に歯磨きをしても、すべてのプラークを取り除くことは難しく、残ったプラークは歯石になります。
歯石はセルフケアでは除去できないため、定期的に歯科医院で専門の器具を使って取り除いてもらう必要があります。
ご自身のケアとプロのケアを組み合わせることが、最も効果的な予防法です。

歯周病は自己判断で放置せず、専門家である歯科医師に相談することが将来の歯と健康を守る第一歩です。
歯周病は初期の自覚症状がほとんどなく、静かに進行するため、「まだ大丈夫だろう」と思っているうちに、手遅れになる可能性も否定できません。
将来的に歯の健康を維持したい方や、美しい歯を維持したい方は、歯科医院での定期的なクリーニングがおすすめです。
日常の歯磨きで取り除けない歯垢や歯石などを除去し、歯周病や虫歯予防をおこなうのがより効果的です。
また、当院では予防歯科に力を入れています。現在歯に違和感を感じている方や不安がある方、ぜひ岡谷市の歯科医院、山田歯科医院までお気軽にご相談ください。