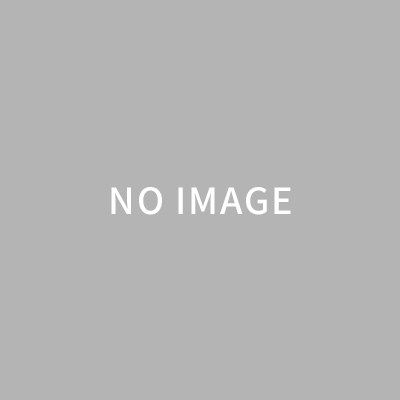「歯磨きしすぎのオーバーブラッシングとは?」
「歯磨きしすぎが歯に与える悪影響を知りたい」
「歯磨きの正しいケアと適切な頻度を確認したい」
上記の疑問をお持ちの方は、人と会う前に何度も歯を磨く習慣があり、歯が削れてきたのではと不安があるのではないでしょうか。
歯磨きのしすぎはオーバーブラッシングと呼ばれ、歯や歯茎を傷つける原因となります。
本記事では、「歯磨きしすぎのオーバーブラッシングについてと正しい磨き方やポイントを解説」を紹介します。
症状レベル別に磨きすぎで傷ついた歯と歯茎の治療法まで紹介しているため、ぜひ最後までご覧ください。
目次

オーバーブラッシングとは、不適切な歯磨き行為を指します。
歯磨きの時間が長い、回数が多いだけが問題ではなく、歯や歯茎にダメージを与える強い力で磨く行為も原因です。
そのため、自身の歯磨き習慣が、大切な歯の寿命を縮めているかもしれません。
良かれと思う毎日の歯磨きが、歯や歯茎を傷つける可能性を理解しておく必要があります。

歯磨きしすぎで起こる症状・デメリットについて、紹介していきます。
それぞれ紹介します。
歯への症状・デメリットは、以下の3つです。
ひとつずつ解説します。
過度なブラッシング圧は、歯と歯茎の境目を楔状に削る「楔状欠損(くさびじょうけっそん)」を引き起こします。
たとえば、歯ブラシを強く当て、横方向に大きく動かすと歯の根元が物理的に摩耗します。
歯の根元は、表面のエナメル質が薄く、柔らかい象牙質が露出しやすいです。
もし放置すると、知覚過敏や虫歯のリスクが高まるため注意が必要です。
歯磨きしすぎは、冷たいものや風がしみる「知覚過敏」の症状を招きます。
歯の表面を覆うエナメル質が削れると、外部の刺激が神経に伝わりやすい象牙質が露出します。
象牙質には歯の神経につながる無数の小さな管が通っており、温度変化などの刺激が直接神経に届き、痛みを感じやすいです。
日常的に歯がしみる症状は、オーバーブラッシングが原因かもしれません。
歯を保護するエナメル質に傷がつくと、虫歯のリスクが高まります。
毎日強い力で歯磨きをした場合、エナメル質の表面に目に見えない無数の傷ができやすいです。
細かい傷に歯垢が付着し、細菌も繁殖しやすくなります。
清潔にしているつもりが、虫歯菌の温床を作っている場合もあります。
歯の健康を守るためには、適切な力加減で磨くのが重要です。
歯茎への症状・デメリットは、以下の3つです。
それぞれ紹介します。
継続的な強い刺激は、歯茎が下がる「歯肉退縮」を引き起こします。
歯茎が痩せて後退すると、本来隠れている歯の根が露出し、歯が以前より長く見えやすいです。
そして、露出した歯の根は、虫歯になりやすく知覚過敏の症状も出やすくなります。
歯茎が下がることは見た目だけの問題ではありません。
硬い歯ブラシで強く磨くと、デリケートな歯茎の粘膜が傷つき出血しやすくなります。
健康な歯茎は。正しい歯磨きで出血しません。
もし歯磨きのたびに出血する場合は、歯周病の可能性も考えられますが、オーバーブラッシングによる物理的な刺激が原因のケースも少なくありません。
歯茎からの出血は、歯磨き方法の見直しが望ましいサインです。
歯茎が防御反応として硬くロール状に盛り上がる「フェストゥーン」が現れる場合もあります。
フェストゥーンは、長期間の過度なブラッシングの刺激から歯茎自身を守ろうとする生体反応です。
健康な歯茎は、シャープなラインを描いています。
一見すると歯茎が引き締まって健康的に見えるかもしれませんが、不適切な歯磨きによって引き起こされた異常な状態です。

歯磨きしすぎにならないためのポイントは、以下の8つです。
ひとつずつ解説します。
自分の磨き方の癖を直すには、歯科医院で専門家の指導を受けるのが確実です。
自分では毎日正しく磨いているつもりでも、客観的に見ると、力が入り過ぎや磨き残しがある場合もあります。
歯科医師や歯科衛生士は、個人の口の状態や歯並びに合わせて、最適な磨き方を指導します。
また、定期的にプロのチェックを受けると、自己流の間違った癖を修正できます。
正しいブラッシング方法を身につけるためには、まず専門家へ相談をするのがおすすめです。
自分の口の状態に合った歯ブラシを選択することで、オーバーブラッシングの予防につながります。
普段から使用している道具が合っていない場合、無意識に力が入りすぎてしまう原因となります。
歯ブラシの毛の硬さは、「ふつう」か「やわらかめ」が基本です。
また、ヘッドの大きさは、上の前歯2本分程度のコンパクトなものが奥歯まで届きやすく推奨されます。
オーバーブラッシングを防ぐためには、「低研磨・低発泡」タイプの歯磨き粉を選びましょう。
研磨剤が多く含まれていると、歯の表面を必要以上に削る場合もあります。
また、発泡性が高い場合、少量でも口のなかが泡だらけになりやすいです。
その結果、すぐに磨けたと錯覚しやすくなるため、磨き残しが多くなる傾向があります。
じっくり丁寧に磨くためには、研磨剤や発泡剤の少ない製品がおすすめです。
歯ブラシは、毛先が開く前の1カ月を目安に交換する習慣をつけましょう。
歯の清掃効果が落ちるため、無意識のうちに歯に強く押し付けてしまい、オーバーブラッシングの原因になりやすいです。
また、毛先が開いた歯ブラシは、歯垢を除去する能力が約6割に低下します。
まだ使えると思っていても、定期的な歯ブラシの交換が歯の健康を守ります。
電動歯ブラシは、歯に軽く当てるだけで、手磨きのようにゴシゴシ動かす必要はありません。
手磨きと同じ感覚で力を入れて動かすと、過剰な力が加わり、歯や歯茎を傷つける原因となります。
電動歯ブラシは、高速な振動や回転によって効率的に歯垢を除去する設計になっているため、適切に使用すれば有効なツールです。
歯磨きの適切な回数は1日2〜3回とされ、タイミングも意識するのが重要です。
歯を磨きすぎも磨かなすぎも、口の健康にとっては問題となります。
とくに重要なのは、就寝前の歯磨きです。
寝ている間に細菌が繁殖しやすくなるため、夜のケアが必要です。
回数だけでなく、汚れがたまりやすいタイミングで磨く意識が大切になります。
酸性の強い飲食物を摂った直後の強い歯磨きは、歯が削れるリスクを高める可能性があります。
お酢や柑橘類、炭酸飲料などを口にすると、一時的に歯の表面のエナメル質が溶かされています。
その状態で強く歯を磨いた場合、エナメル質が削れやすいです。
ただ、習慣的に酸性のものを摂取していなければそこまで気にする必要はなく磨かずに放置するよりは磨いた方が良いので、酸性の物を摂取した直後の歯磨きは水で口をゆすいでから磨くのが望ましいです。
鏡で自分の歯茎の状態を定期的にセルフチェックする習慣が、オーバーブラッシングの早期発見につながります。
自分の口の中の変化に気づくことが、深刻なトラブルを防ぐためには重要です。
もし「以前より歯が長くなったように見える」「歯の根元がしみる」などの変化がある場合は、歯茎が下がっているサインかもしれません。
日々の観察によって、口内環境の変化を見逃さないようにしましょう。

歯磨きをする若い日本人の男性
歯磨きしすぎを防ぐ正しい磨き方は、以下の3つです。
それぞれ紹介します。
スクラビング法は、歯の表面の汚れを落とすのに効果的な磨き方です。
歯ブラシを歯の面に直角に当て、歯ブラシの毛先が歯と歯の間に入るようにします。
その状態で、5mm程度の幅を目安に、歯ブラシを細かく振動させるように動かします。
力を入れず、優しく小刻みに動かすことがポイントです。
とくに歯並びが良い人や、食べ物を噛む面の清掃に適している方法です。
バス法は、歯周病の予防や改善に特に効果的な磨き方です。
歯と歯茎の境目に、歯ブラシを45度の角度で当て、毛先を歯周ポケットに少し入れるようなイメージで、優しく挿入します。
そして、歯ブラシを前後に細かく振動させ、歯周ポケット内の歯垢を掻き出します。
力を入れすぎると歯茎を傷つけるため、軽い力でおこなうのが重要です。
フォーンズ法は、子どもや手先を細かく動かすのが苦手な方でも実践しやすい簡単な磨き方です。
上下の歯を軽く噛み合わせた状態で、歯ブラシを歯の表面に当て、大きな円を描くように、歯ブラシをくるくると回しながら磨きます。
歯の外側の面を効率よく磨けるため、楽しみながら歯磨き習慣を身につけたいお子様にもおすすめです。

症状レベル別の磨きすぎで傷ついた歯と歯茎の治療法は、以下の5つです。
ひとつずつ解説します。
軽度の知覚過敏は、市販の知覚過敏用歯磨き粉で、症状を緩和できる場合があります。
歯磨き粉には、主に「硝酸カリウム」や「乳酸アルミニウム」といった薬用成分が含まれています。
硝酸カリウムは、歯の神経への刺激の伝達をブロックする働きがあります。
手軽に始められる対策として、日々のセルフケアに知覚過敏用歯磨き粉を取り入れることで、しみる痛みを和らげていきましょう。
歯科医院で高濃度のフッ素(フッ化物)やコーティング剤を塗布することで、歯質を強化し、しみる症状を抑えられます。
フッ素(フッ化物)には、歯の再石灰化を促進し、エナメル質を酸に溶けにくい性質に変える効果があります。
また、露出した象牙質の表面をコーティング剤で保護することで、外部からの刺激の物理的な遮断も可能です。
知覚過敏の症状を、根本を改善することが期待できるため、定期的な塗布がより効果的です。
楔状欠損によって削れてしまった部分は、歯科用のプラスチック(レジン)で埋める治療が有効です。
保険適用で治療が可能で、歯の根元がさらに削れるのを防ぐ効果も期待できます。
歯の削れた部分をきれいに清掃したあと、歯の色に合わせたレジンを詰めて、光を当てて固めます。
治療後はしみる症状が改善されるだけでなく、見た目の自然な回復も可能です。
歯の削れの原因に歯ぎしりも考えられる場合、歯科医院で自分専用のマウスピースを作製するのが有効です。
就寝中に無意識におこなわれる歯ぎしりは、歯に非常に強い力をかけ、摩耗を進行させます。
そのため、就寝中にマウスピース(ナイトガード)を装着することで、歯への負担を軽減できます。
歯ぎしりは、根本的な原因へのアプローチが、歯を守るためには不可欠です。
重度の歯肉退縮に対しては、下がった歯茎を回復させる「歯肉移植術」といった外科的な治療法があります。
主に上顎の口蓋から歯茎の一部を採取し、歯茎が下がってしまった部分に移植する方法です。
結果的に、露出した歯の根を覆い、見た目を改善できます。
歯周組織再生療法のひとつであり、専門的な技術を要する高度な治療法です。
ただ適応が限られるため、歯科医院で相談しましょう。

歯磨きしすぎに関するよくある質問を、以下にまとめました。
それぞれ紹介します。
「磨いている」は行為を指し、「磨けている」は歯垢を除去した結果です。
歯磨きにおいて、時間や回数より、歯垢が落ちた成果が重要です。
磨き終わりに舌で歯を触り、ツルツルした感触があれば磨けています。
強く磨いても、歯は白くなりません。
逆に、エナメル質を傷つけてしまい、黄ばんで見える原因になります。
着色汚れがある場合は、歯科医院のクリーニングやホワイトニングで落とすのが適切な方法です。
酸性の強い飲食後は歯の表面は柔らかくなるため、すぐに磨くと歯を傷つけるリスクがあり、一部本当です。
しかし、一般的な食事の場合、食後なるべく早く磨くことが虫歯予防の基本です。
歯磨き粉をたくさん付けても効果は高まりません。
泡立ちで磨けたと錯覚し、磨き残しの原因になります。
歯磨き粉の適量は、歯ブラシの「1.5cm〜2cm」を目安として、薬用成分を作用させるために丁寧に磨きましょう。
正しい使い方であれば、問題ありません。
手磨きのようにゴシゴシ動かすと、歯や歯茎を傷つけるリスクが生じます。
製品の取扱説明書に従って、歯に軽く当てて使用するのが大切です。
フロスや歯間ブラシは、使い方を間違えると歯茎を傷つける原因になります。
無理に歯茎へ押し付けたり、乱暴に動かしたりするのは避けてください。
歯ブラシと同様に、自分に合ったサイズを選び、正しく使用するのが重要です。
お子さんの場合、本人だけに任せてしまうと強く磨きすぎたり、同じところばかり磨いたりしている場合があります。
ただ、年齢によっては技術的に難しいため、保護者の仕上げ磨きが重要です。当て方や強さやコツは歯科医院で教わりましょう。

歯磨きしすぎのオーバーブラッシングは、良かれと思って歯を強く・長く磨くことが、かえって歯や歯茎にダメージを与えてしまう状態です。
毎日の歯磨きの習慣が、知らず知らずのうちに大切な歯や歯茎を傷つけていたかもしれません。
もし少しでも歯磨きや歯の症状などで不安な点がある場合は、自己判断で悩まずに、かかりつけの歯科医院に相談してください。
専門家である歯科医師や歯科衛生士は、あなたの口腔内の状態を正確に診断し、あなたに合った最適なケア方法を指導してくれます。
また、当院では予防歯科に力を入れています。現在歯に違和感を感じている方や不安がある方、ぜひ岡谷市の歯科医院、山田歯科医院までお気軽にご相談ください。