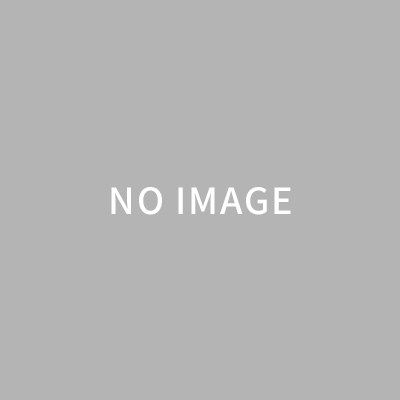「歯周病のセルフチェック方法とは?」
「そもそも歯周病とは?」
「歯周病を予防する方法が知りたい」
上記の疑問をお持ちの方は、歯ぐきの腫れや下がりが不安もしくは歯が少し揺れる気がして食事がしにくいことにお悩みがあるのではないでしょうか。
歯周病は初期症状が分かりにくいため、セルフチェックは早期発見の重要なきっかけになります。
本記事では、「歯周病のセルフチェック方法と予防するための方法」を紹介します。
歯周病の基本についても最初に解説しているため、ぜひ最後までご覧ください。
目次

歯周病は、歯そのものではなく歯を支える歯ぐきや骨が、細菌によって静かに破壊されていく病気です。
初期段階では、痛みなどの自覚症状がほとんどありません。
「静かなる病気(サイレント・ディジーズ)」とも呼ばれ、気づかないうちに進行して最終的に歯が抜けてしまう場合もあります。
自覚症状がないまま悪化し、歯を失う原因となるのが歯周病です。

歯周病セルフチェックリストとして、以下の15項目があります。
歯周病は初期症状が分かりにくいため、セルフチェックは早期発見の重要なきっかけになります。
もしひとつでも当てはまれば歯周病の可能性があり、複数該当する場合はすでに進行している恐れもあるため、早めに歯科医院を受診しましょう。
歯磨きの際の出血は、歯ぐきが炎症を起こしているサインで、歯周病の代表的な初期症状です。
健康な歯ぐきは、歯ブラシが当たった程度では出血しません。
出血するのは、歯周病菌の出す毒素で歯ぐきに炎症が起きている証拠であり、体が「ここに細菌がいます」と教えてくれる警告サインです。
歯磨き時の出血は、歯周病の始まりを知らせる重要な手がかりとなります。
歯ぐきが赤く腫れたり、ぶよぶよと引き締まりがなかったりする場合、歯周病が疑われます。
健康な歯ぐきは薄いピンク色で引き締まっていますが、歯周病菌による炎症が起こると充血し、赤みを帯びて腫れぼったくなります。
この状態は歯肉炎や歯周炎の典型的な症状であり、歯ぐきの色や形の変化は見逃せない健康のバロメーターです。
歯が以前より長くなったように見えるのは、歯周病の進行によって歯ぐきが下がっているサインかもしれません。
歯周病が悪化すると、歯を支えているあごの骨が溶かされてしまいます。
歯ぐきは骨に沿っているため、骨が吸収されると同時に後退し、本来隠れている歯の根の部分が見えてきてしまうのです。
歯ぐきが下がり歯の露出部分が大きくなることは、歯周病が進行している証拠です。
歯と歯の間に食べ物が詰まりやすくなったと感じるなら、歯周病が原因の場合があります。
歯周病で歯を支える骨が弱くなったり歯ぐきが下がったりすると、歯が少しずつ動いてしまい、以前はなかったすき間が生まれやすいです。
すき間に食べ物の繊維などが挟まりやすくなるため、歯並びの変化は歯周病の進行を疑うきっかけになります。
指で押したときに歯がグラつくのは、歯周病がかなり進行している危険なサインです。
歯はあごの骨(歯槽骨)にしっかり支えられていますが、歯周病が重症化するとこの骨が広範囲に溶かされ、歯の支えを失ってしまいます。
土台が不安定になれば歯が動揺するのは当然で、抜歯に至る可能性も考えられるため、決して放置してはならない症状です。
歯ぐきから白い膿が出る場合、歯周病が活発に進行していると考えられます。
膿は、歯と歯ぐきの溝(歯周ポケット)に侵入した細菌と、体を守る免疫細胞(白血球など)が戦ったあとの死骸です。
膿が出ているということは、お口のなかで今まさに細菌との戦いが起きている証拠であり、体が発するSOSサインとなります。
朝起きたときのお口のなかのネバつきは、歯周病菌が増殖しているサインかもしれません。
就寝中は唾液の分泌量が減って細菌が活動しやすくなるため、口内細菌が粘着性のある物質を作り出します。
お口のなかの細菌が多いほどネバつきは強くなる傾向があり、この不快な症状はお口の衛生状態が悪化していることの表れです。
なかなか消えない口臭は、歯周病が原因かもしれません。
歯周病菌はタンパク質を分解する過程で「揮発性硫黄化合物(VSC)」と呼ばれる強い臭いを放つガスを発生させ、これが特有の口臭の主な原因となります。
丁寧に歯磨きをしても口臭が改善されない場合は、歯周ポケットの奥深くなど、自分では清掃できない場所で細菌が繁殖している場合があります。
虫歯ではないのに冷たいものがしみる場合、歯周病による知覚過敏の可能性が考えられます。
歯周病で歯ぐきが下がると、本来保護されているはずの歯の根(歯根)が露出します。
歯根の表面にある象牙質には神経につながる無数の管が通っているため、外部からの刺激が直接伝わり、「キーン」とした痛みを感じやすいです。
硬いものを噛んだときに痛みや違和感を覚えるのは、ときは、歯を支える組織が弱っている証拠です。
可能性があります。
歯とあごの骨の間にはクッションの役割を果たす歯根膜という組織があります。
歯周病が進行すると歯根膜や周辺の骨にまで炎症がおよび、噛んだときの強い力を吸収・分散できなくなるため、痛みや歯が浮いたような違和感として感じやすいです。
喫煙は、歯周病の発見を遅らせ、進行を早める大きなリスク因子です。
たばこに含まれるニコチンは血管を収縮させ、歯ぐきの血行を悪化させます。
すると、歯周病への抵抗力が落ちるだけでなく、炎症のサインである歯ぐきの腫れや出血が起こりにくくなり、自覚症状がないまま水面下で重症化しやすくなります。
ストレスが原因で起こる歯ぎしりや食いしばりは、歯周病を悪化させる一因です。
歯ぎしりや食いしばりは、食事のときにかかる力の何倍もの過剰な力を歯周組織に継続的にかけます。
強い力は、すでに歯周病で弱っている歯周組織に追い打ちをかけ、骨の破壊を加速させる要因です。
口呼吸の習慣は、歯周病のリスクを高める可能性があります。
口で呼吸をしていると口内が乾燥し、細菌の増殖を抑えたり汚れを洗い流したりする唾液の効果が十分に得られなくなります。
その結果、歯周病菌が繁殖しやすい環境が作られてしまうため、健康を保つには鼻呼吸を意識することも大切です。
放置している虫歯や抜けたままの歯は、歯周病の温床になり得ます。
虫歯の穴や合わない被せ物の段差、歯が抜けたスペースの周りなどは歯垢が溜まりやすく、細菌の格好のすみかです。
そうした場所から歯周病が始まったり悪化したりするため、問題箇所はきちんと治療しておくことが歯周病予防にもつながります。
糖尿病などの全身疾患や、体の免疫力が低下する状態は、歯周病と深く関連しています。
とくに糖尿病は歯周病の進行を早め、逆に歯周病の治療で血糖値が改善することもあり、相互に影響します。
また、疲労やストレスで体の抵抗力が落ちているときも歯ぐきの炎症は悪化しやすく、歯周病は全身の健康を映す鏡です。

歯周病を予防するための方法は、以下の5つです。
歯周病を効果的に予防するには、日々のセルフケアと歯科医院でのプロフェッショナルケアの両立が不可欠です。ひとつずつ解説します。
歯周病予防の最も重要な基本は、原因である歯垢を毎日の歯磨きで徹底的に除去することです。
歯周病は、歯垢に潜む細菌が引き起こす感染症のためです。
とくに、細菌のすみかになりやすい歯と歯ぐきの境目「歯周ポケット」を意識し、毛先を45度の角度で当てて優しく磨くなど、正しい方法を実践しましょう。
歯周病予防の効果を高めるには、歯ブラシに加えフロスや歯間ブラシを毎日使うことが極めて重要です。
歯ブラシの毛先が届きにくい歯と歯の間は歯垢が最も残りやすく、過去の研究結果では、歯ブラシだけでの歯垢除去率は58%とされています。
引用元:Interdental Brush と Dental Floss の清掃効果について 山本 昇, 長谷川 紘司, 末田 武, 木下 四郎|日本歯周病学会会誌|J-STAGE
歯間から始まることが多い歯周病の予防には、これらの清掃用具の使用が不可欠です。
歯周病予防には、歯ぐき自体の抵抗力を高める生活習慣も大切です。
歯周病は細菌感染症ですが、体の免疫力が進行に大きく関わります。
栄養バランスの取れた食事や十分な睡眠で免疫力を維持し、禁煙で歯ぐきの血流を改善するなど、全身の健康を考えることが、結果的にお口の健康を守ることにも直結します。
自分では取れない歯石を除去するため、定期的に歯科医院で専門的なクリーニングを受ける必要があります。
歯垢が硬くなった歯石は、歯ブラシでは取り除けません。
歯石の表面はザラザラしていて新たな歯垢が付着する足場となり、歯周病を悪化させる原因になるため、プロの手で除去してもらいましょう。
歯周病から歯を守るには、自覚症状がなくても定期的に歯科検診を受けることが最も確実です。
歯周病は初期段階ではほとんど症状が現れず、痛みなどが出てからでは手遅れに近いことも少なくありません。
問題を感じていない段階で専門家のチェックを受けることで、ごく初期に発見し、簡単な治療で進行を食い止められます。

大切な歯を歯周病から守るには、日々のセルフチェックを習慣にし、お口の変化にいち早く気づくことが重要です。
この記事で紹介したチェックリストで、ご自身の状態を確認してみてください。
もしひとつでも当てはまる項目があれば、それは歯ぐきが発しているサインかもしれません。
将来的に歯の健康を維持したい方や、美しい歯を維持したい方は、歯科医院での定期的なクリーニングがおすすめです。
日常の歯磨きで取り除けない歯垢や歯石などを除去し、歯科予防をおこなうのがより効果的です。
また、当院では予防歯科に力を入れています。現在歯に違和感を感じている方や不安がある方、ぜひ岡谷市の歯科医院、山田歯科医院までお気軽にご相談ください。